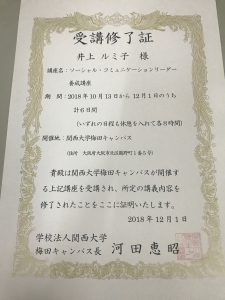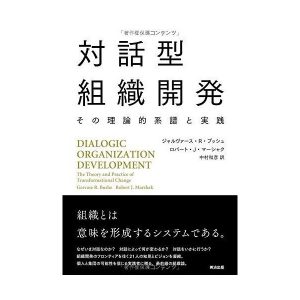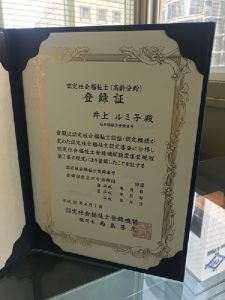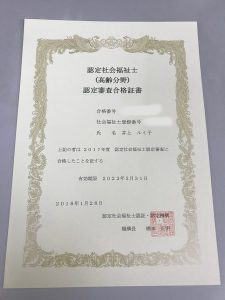シグネチャーパビリオン「Dialogue Theater -いのちのあかし-」。
河瀨直美監督がプロデュースするこの企画は、「対話」を通じて、世界の至るところにある“分断”を明らかにし、その解決を試みる実験場でした。
「対話」をあらゆる角度から捉え、介護の現場をより良くしたいと考えている私にとって、まさに心に響く活動でした。
オーディションを経て、ワークショップに参加し、本番で育成対話者として登壇する貴重な経験をさせて頂きました。
その日のテーマをどう捉え、どのように対話を温めていくかは、対話者一人ひとりに委ねられています。
私は仕事柄、人の生死に立ち会い、苦悩や憤りに向き合う日々を送っています。人が生きる上での本質的な問いに出会い、自分の心の奥に気づく瞬間——そこに、新たな景色”幸”が広がる可能性を感じました。
人は分かり合えないからこそ、分かり合おうとする。
それを諦めないからこそ、真意の接点が見えてくる。
生きていることの尊さを実感できた時、争いの愚かさに気づく。
論文でも言及しましたが、改めて、医療や介護の現場には「対話」が中心にあるべきだと痛感しました。
この経験を仕事に活かし介護の現場をより良くしていくことこそが、万博活動に参加させて頂いた恩返しになると思っています。
最後に、パビリオン関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
写真は、万博最終日、卒業式と打ち上げシーンです。