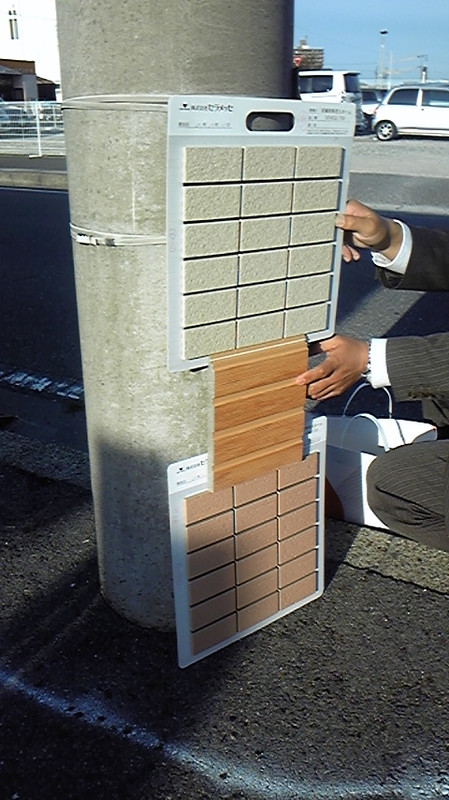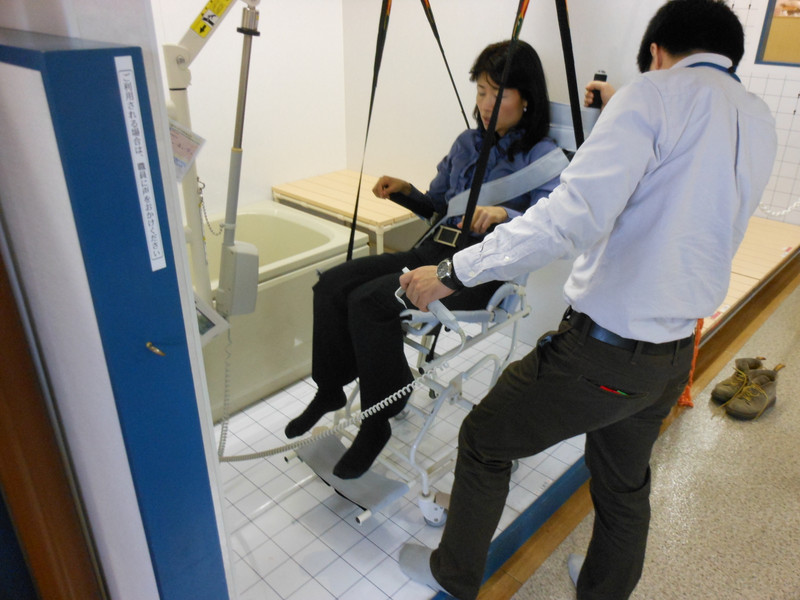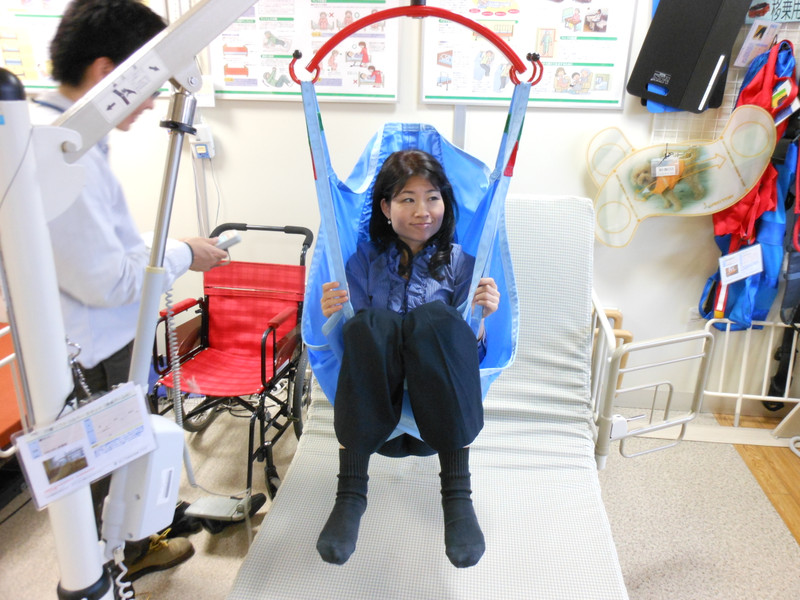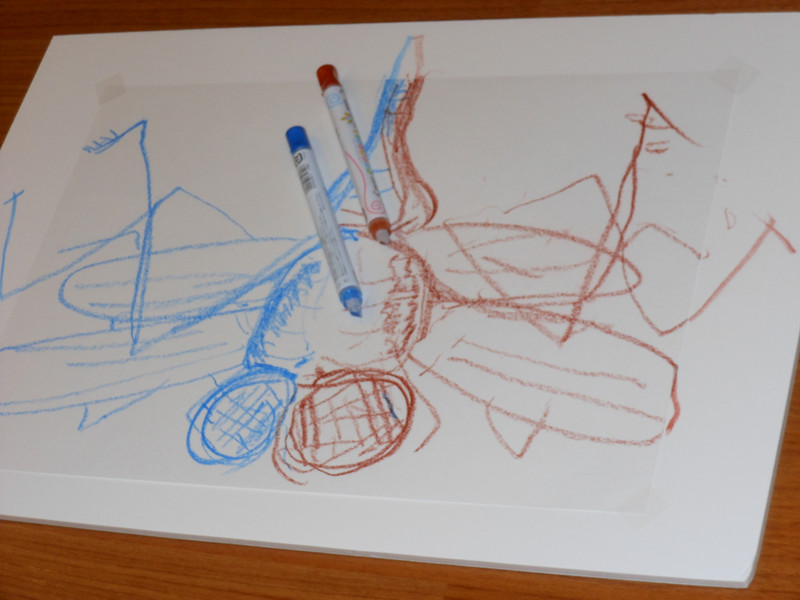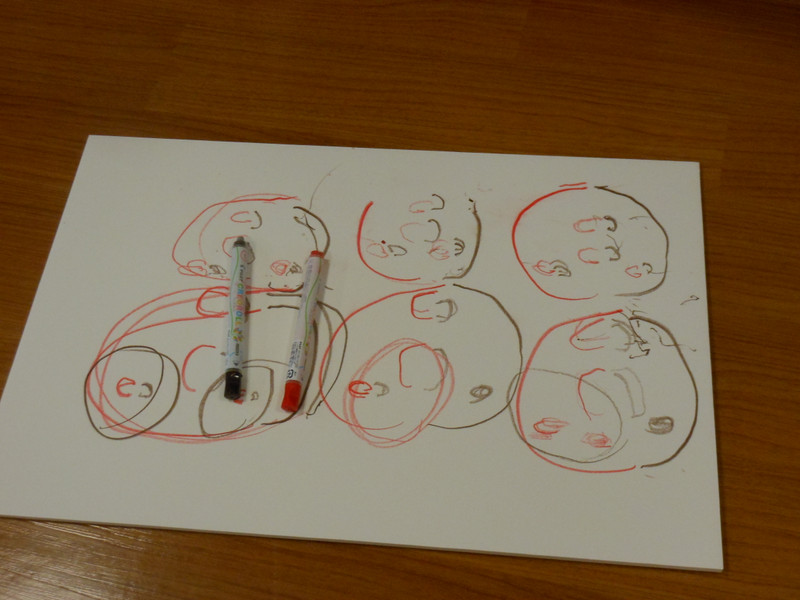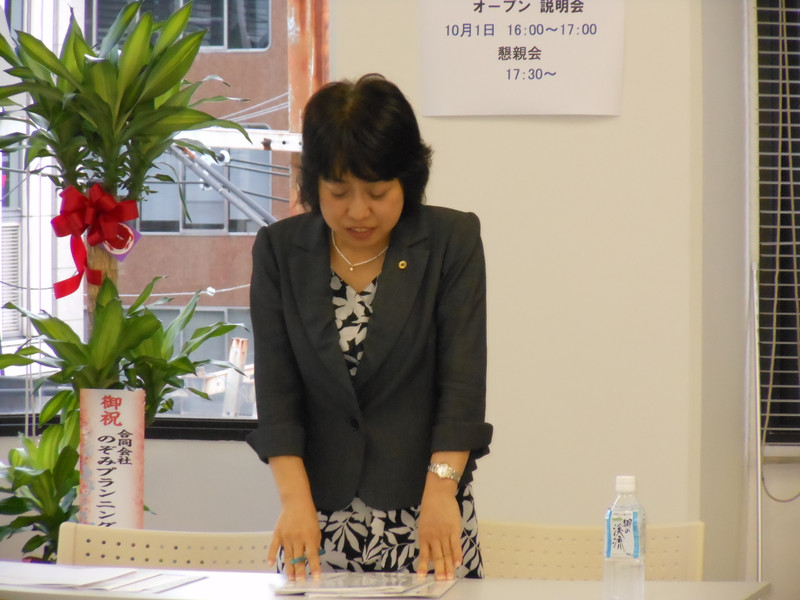今回のテーマはトラブルのもと「心理的ゲーム」です。
ゲーム分析とは、
会話で表面的にはまことしやかな
一連の交流(相補的交流)が行われてるとします。
しかし一方(プレイヤー)の裏面に
本音のメッセージが隠されている場合、
それを果たそうとするプレイヤーの自我が、
相手を刺激して、ゲームを仕掛けていき、
相手のネガディブな感情を挑発し、
ゆがんだ形でストロークの交換を図ろうとするそうです。
そして結末は、もやもやした感じや悪感情が残ります。
身近でいらっしゃいませんか?
その人と話しをすると、
どうしていつもこんな話の向きになるんだろう?
どうしていつもこんな嫌な気持ちになるんだろう?って。
最初から展開や結論が予測できてしまうほどパターン化
されている人もいます。
例えば夫と妻の心理ゲームを例に挙げます。
夫 洗濯しておいたぞ (仕掛け人)
妻 ありがとう、助かるわ。 (乗せられる人)
夫 沢山あったぞ。
妻 そうでしょう。 (応答)
夫 3回も洗濯を回したんだぞ。
妻 ここ2、3日、忙しくてできなかったの。
夫 部屋も散らかっているし、流しには食器が一杯。
毎日何をしているんだ! (はぐらかし)
妻 家の中の仕事が山ほどあるのよ。あなたこそ何よ!
毎晩、残業って帰りが遅いけど、外でなにしているか
分かったもんじゃないわ。
夫 お前こそいつも家にいないじゃないか。
一体何をしているんだ! (混乱)(本当に言いたいこと)
妻 ちょっと洗濯しただけで偉そうに言わないでよ。
もうしてもらわなくていいわ!
夫 二度とするか。 (結末)
妻 二度といらないわよ。
これは夫婦の会話ですが、
職場の同僚や上司、友人との会話でも同じです。
気がづくと、
やっつけられてしまっていたり、
こちらも興奮して思わぬことを言葉にしてみたりなど。
程度によっては、
嫌な感情→悪感情の継続→破壊的になり
時に殺人などに発展していきます。
できれば相手に巻き込まれずにしたいもの。
ゲームの止め方としては、
①ゲームの存在に気づく、自分が何をしているか理解する。
②時間の経過と、自分のとった役割を振り返る。
③ゲームにのらない自分をつくる。
④自分自身や他人を無視、軽視しない。
⑤程度の重いゲームを軽いゲームに抑える。
⑥結末の悪感情を取り入れない。
⑦最悪の時は逃げる。
私達は職場でも学校でも家庭でも、
自分と合う人ばかりでないことは100も承知。
そして日常会話の多くにこのゲームが展開されています。
それを客観的に理解しつつ、
巻き込まれない自分を持つことが大切だと思いました。