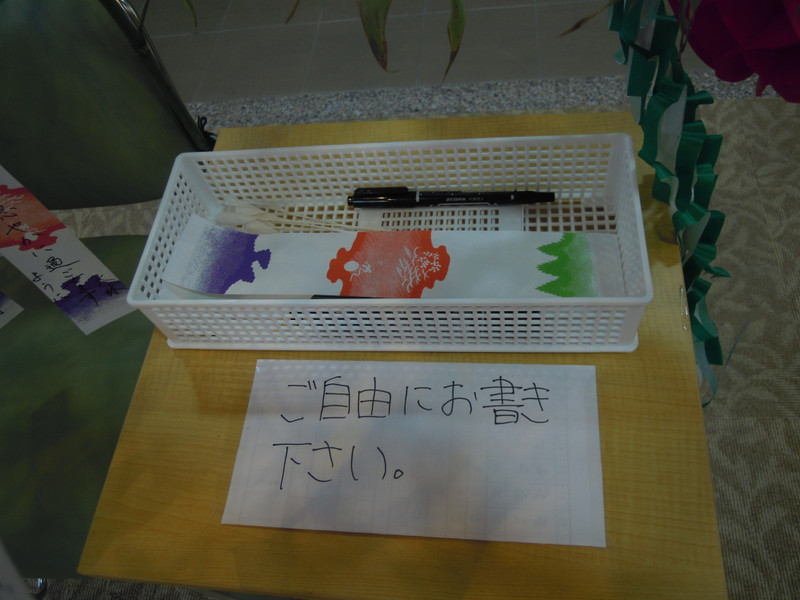「病院に連れていってくれ~先生と約束しているんだ~」と
訴えてこられる入居者の方。
それぞれの認知症に合わせた対応が求められます。
環境や話題を変えると落ち着く方もいらっしゃいますが、
この方はひたすら訴えられていました。
ある職員が「どうして病院に行きたいの?」とその理由を
一生懸命に聴き、原因を探ろうとしています。
「足が痛い、先生と約束している」の繰り返し。
昼から往診に来られることを伝えても、
約束へのこだわりは強く、訴えは続きます。
機転をきかせ、車イスで隣のクリニックへ行くと、
外来が終了した直後で先生が快く対応してくださいました。
興奮は徐々におさまり、皆さんと一緒に昼食をとられました。
その後こだわりの理由が分かりました。
以前他科受診をした際、次回の予約を入れてきたが、
2回目は家族のみ病院に行かれた経緯があるそうです。
確かにご本人の体験は”先生との約束”で止まっていてます。
足の痛みが約束を思い出させ、
「行かねば、約束しているのに」そんな責任感が今回の行動
につながったのでは・・・。
「病院に行かねば!先生も約束時間を守らんか!」
そんな訴えだったようにも感じました。
本人にとって納得が出来る関わりをしなければ、
訴えは繰り返されるだけ。
安易に認知症が進んだと結論づけることのないよう、
職員の意識の持ち方が大切になってきます。