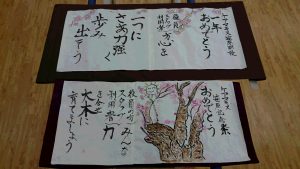ソーシャルワークアプローチ
本日は、認定社会福祉士特別研修修了判定審査結果の合格通知を頂きました。
改めて理論をベースとしたソーシャルワークアプローチを振り返る良い機会となりました。
クライエントには平等に援助を受ける権利があるはずですが、ワーカー個人の経験則から生まれるパターン化されたアプローチにその保証はありません。
日々の実践においては、どうしても感情や個人的価値をバロメーターにしがちですが、その段階で社会福祉士の倫理綱領を遵守できていない事を自覚致しました。
理論やアプローチの意味するところを読み解けば読み解くほど、起こっているかもしれないリスクにも気づかされます。
確かにソーシャルワークの展開では早急な対応を余儀なくされ、問題解決アプローチの場面も多いと思います。
その際、一見問題は解決しても、その後のクライアントの生活や周囲との関係性が継続していく事を考えた場合、時に暴力的な介入になっていないかどうかの振り返りも重要だと思いました。
なぜならソーシャルワーカーは、ある意味「問題状況に巻き込まれない中立な立ち位置」が重要だと言われ、いつかソーシャルワークを終了させていく事がミッションとなっています。
言葉を選ばずに表現すると、私達にはいつか去る場所がある訳ですが、クライアント自身はどんな結果になっても、その生活や関係性の継続が余技なくされる、いわゆる逃げる事ができない状況である事を鑑み、常に責任ある関わりを意識すべきだと思いました。
今後も、実施モデルの正しい理解と各々のモデルの関連性とリスクを十分に理解した上で、適切なアプローチを選択する事が重要であると感じました。
今回は主に、システム理論、エコロジカルモデル、エンパワーメント・アプローチ、ジェネラリスト・アプローチなどに注目しました。